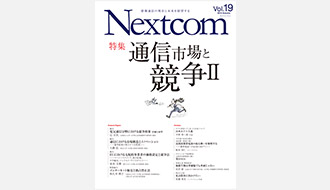2014/09/01
極限生物は単細胞でも単純じゃない
なぜ、それほど過酷な環境、極限状態で生きるのかと問いたくなる生物がいる。彼らの言い分は「生命の起源はこっち。ここが天国」かもしれない。
住めば都
 好塩菌ハロモナス
好塩菌ハロモナス
極限生物とは、ふつうの生きものなら死んでしまうような極限環境あるいは極限条件でも生きていける生物です。英語ではextremophileといい、極限(extremo-)を好む(-phile)という意味ですが、"好む"のではなく"耐える"ものも含めて、極限生物といいます。
その極限環境ですが、具体的には高熱の火山や極寒の南極、ものすごい水圧で暗黒の深海、からからに乾燥した砂漠、手を入れると皮膚が溶けてぬるぬるするようなアルカリ性の湖など、人間から見たら酷いところです。なかには、酸が強すぎて卵の殻が溶けてしまうので温泉玉子がつくれないという、まるで冗談のような酸性温泉もあります。
そんな苛酷な環境でも「住めば都」で、そこで生きている生物には苛酷どころか天国のようかもしれません。苛酷とか極限とかいうのは人間中心の発想で、自然界を広く見わたすと、人間が生きていける環境や条件なんてすごく狭いということがわかります。極限生物の命を知ることで、自然界における人間の位置を客観的・相対的に眺めることができるようになるのです。
いきにくい場所という最前線

極限環境のことを私はよく「いきにくい場所」と言っています。実はこれ、「生きにくい場所」と「行きにくい場所」の掛け言葉です。前者の「生きにくい」は生きるのが大変なところを指します。後者の「行きにくい」は深海や南極、砂漠、火山など、アクセスしにくいところで、私は「辺境」と呼ぶこともあります。
辺境は英語でfrontier、フロンティア精神(開拓精神)のフロンティアであるとともに、仕事や研究の"最前線"でもあります。したがって、私が「辺境生物学」というとき、「極限環境における生物研究の最前線」という気持ちを込めています。
極限生物は、そのほとんどが目に見えないほど小さな生物、すなわち微生物です。サイズの大小はありますが、大腸菌や乳酸菌など、代表的な微生物の大きさは1000分の1 ミリくらい。われわれ人間の細胞(一人あたり約70兆個)と比べると、体積にして1000分の1から1万分の1以下しかありません。それほどに小さな微生物は、ほとんどが単細胞。ふつう、単細胞というと"物事を深く考えない単純な人"を指します。ところが、微生物の単細胞は単純どころか、われわれの常識を超えたすごい能力を秘めているのです。
微生物のすごい能力
たとえば、ダイオキシンなどの環境汚染物質や環境ホルモンは人工的なもので、自然界にもともとなかったのですから、自然界の微生物にもそれを分解する能力はなかったはずです。ところが、分解菌がいつの間にか出てくるのです。人間が汚染物質をまき散らかしてから急に進化したのでしょう。
進化といえば、地球で最初に生まれた命はたぶん微生物だったことでしょう。生まれたばかりの弱々しい微生物が、高温で酸性で無酸素の苛酷な原始環境を生き延びてくれました。今いる地球上の生きものはすべて、そんなすごい微生物から進化してきたのです。そして、これからも。
文:長沼 毅 絵:大坪 紀久子
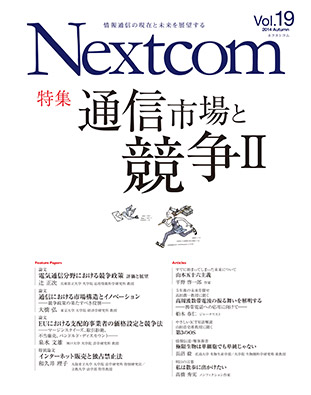
上記は、Nextcom No.19の「情報伝達・解体新書 彼らの流儀はどうなっている?」からの抜粋です。
Nextcomは、株式会社KDDI総研が発行する情報通信誌で、情報通信制度・政策に対する理解を深めるとともに、時代や環境の変化に即したこれからの情報通信制度・政策についての議論を高めることを意図として発行しています。
詳細は、こちらからご覧ください。
長沼 毅(Takeshi Naganuma)
広島大学 生物生産学部/大学院 生物圏科学研究科 准教授
1961年生まれ。筑波大学大学院生物科学科修了。理学博士。
僻地でのフィールドワークが多く、「科学界のインディ・ジョーンズ」などと紹介される。
著書は『辺境生物探訪記』(光文社新書)、『生命とは何だろう?』(集英社インターナショナル)など多数。
presented by KDDI
参考情報